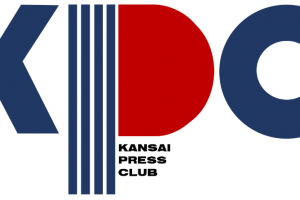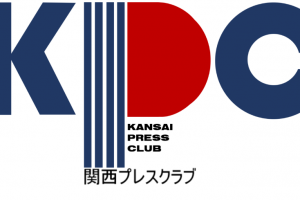藤沢周平さんの「三屋清左衛門残日録」をまた読んでいる。藩の要職を退き隠居生活に入った主人公の清左衛門が、図らずも様々な事件や政争に巻き込まれるが、培った経験と人望で解いて行く。「残日録」とは清左衛門が記す日記の題で、「日残リテ昏ルルニ未ダ遠シ」との意だ。この小説を初めて読んだのは30年余り前、当時はあまり響かなかったが、今しみじみと名作のページを繰っている。
設立30周年事業の記念講演会「伝説の記者」は、各分野で活躍してきた「現代の清左衛門」のみなさんに登壇を願った。野球を中心に70年にわたってスポーツ取材をしてこられた元日本経済新聞記者の浜田昭八さん(90)は、数々の名監督、名選手の懐に飛び込んできたコツを「けっして嘘をつかないこと」と、誠実な取材姿勢の大切さを言われた。
産経新聞文化部特別客員記者の亀岡典子さんは人形浄瑠璃、上方歌舞伎などの伝統芸能を40年余りにわたって担当してきた。「取材を続けると、どれだけの思いで芸に向かっておられるかがわかってくる。尊敬の念を持って記事を書いている」と、たどり着いた境地を語った。
モンゴルやシベリアに取り残された日本兵抑留者の実態解明をライフワークにする元読売新聞大阪本社論説委員の井手裕彦さん(69)は「記録を入手した抑留死者全員の身元を特定するまでゴールはない」と来夏、再びモンゴルに渡る予定だ。
元朝日放送報道局プロデューサーの石高健次さん(73)は体を張った取材で、横田めぐみさんの行方不明が北朝鮮による拉致であることを突き止め、両親に報告、ついに政府をも動かした。今も「国民の生命を守るという意識が政府にはなさすぎる」と憤り、次の番組の構想を練る。いずれも、未だ眩しい残照で後進を導いていただいた。
SNSを含むネットメディアが日常に広がり、「コタツ記事」やフィルターバブルといわれる現象も横行している。前者は現場に行かずネット検索などで取材の手間を省いた記事、コタツに温まりながら書くようなものとの例えだ。ニュースの受け手はネット技術の発達で、自分が見たい情報だけしか見えない、まるで泡(バブル)に包まれたような環境に陥る。それが後者。
「伝説の記者」ならずとも、われわれは事件事故が起きると現場に走り、関係者に対面で話を聞くことが取材の鉄則と教えられた。不幸にも犠牲になられた方の生前の顔写真を紙面に載せるため、「„がん首〝がとれるまで支局に帰ってくるな」とデスクから厳命された世代だ。
今の状況は想像を絶するが、ネット記事を「人工添加物いっぱいのインスタント食品」と例えれば、勝つのは簡単だ。「とれたての魚や野菜、新鮮な肉など自然素材をふんだんに使った手作り料理」の方がおいしく、健康に良いのに決まっている。物事の本質を対面で取材して伝えるという報道の流儀は、いつの世も変わらない。
関西プレスクラブのメンバーは、新聞、放送各社の部長クラス以上、いわば「清左衛門」が主軸だ。モラハラといわれようと、この流儀を若手のみなさんにしつこく浸透させていただきたい。「昏ルルニ未ダ遠シ」。「オールドメディア・パーソン」にトーチをつなぐことが、「オールド・メディアパーソン」の務めだ。
(田中 伸明)