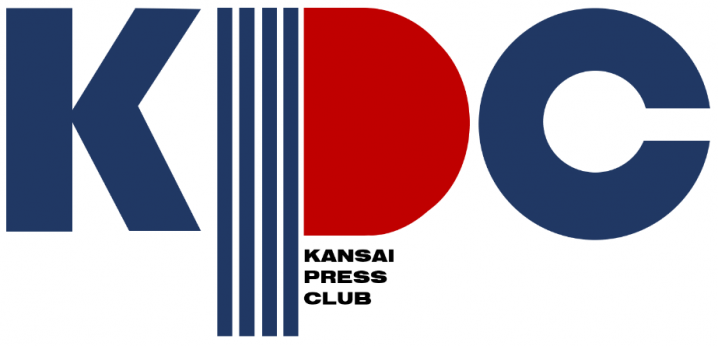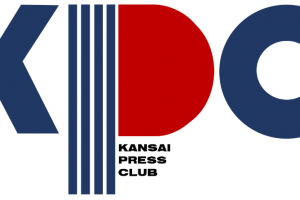関西プレスクラブ総務委員長
(朝日新聞大阪本社社会部長)
羽根 和人
毎年春、朝日新聞社会部には「新人」たちが赴任する。地方勤務を経て、初めて本社に配属される入社5年目くらいの記者だ。
社会部での配置先は大阪市内の警察署を担当する「市内班」や府下支局。ここでどれだけ活躍し、成長できるか――。今年の新人たちも4月1日、引き締まった顔つきでやってきた。
新型コロナウイルスの緊急事態宣言が出たのはその1週間後だ。
「マスク外すな!」
ある新人の男性記者は夜の警察署回りで課長にあいさつしようとしたら、いきなり厳しい調子で言われた。「顔を覚えてもらわないと」とマスクをずらしたからだ。
別の署では、課長から「あまり近づかんといてね」と言われたという。5月になると、カウンターに透明のカーテンがぶら下げられ、取材しにくい雰囲気がさらに強まっていった。
「相手の顔が見えないし、相手も私がマスクを外したら、誰だか分からないんじゃないですかね」。彼は不安を口にする。
社会部の取材チームのキャップたちに聞くと、ウイルスの影響はあらゆる現場に及んでいた。
教育キャップは、学童保育所に取材依頼すると、相次いで断られたという。「外部の人が入ることに保護者の理解を得られない」という理由が多数だった。高校野球取材班は、そもそも部活動という「現場」がなくなった。
記者たちも感染拡大防止に必死だった。マスクの着用や消毒、検温は当然。取材時間を短くするために事前に質問をメールで送ったり、「離れて話しましょう」と持ちかけたりした。それでも対面取材の申し入れは断られ、「オンラインでしか受けない」と言われることがしばしばだった。
「朝駆け・夜回り」も拒まれるケースが出てきた。「感染防止が、取材拒否のいい口実になった印象がある」と担当記者は話す。一方、別の当局取材の担当者はこの事態を逆手に取り、「対面取材できないことを理由にして、携帯電話の番号などの連絡先を集めるようにした」という。
こうした状況と一線を画していたのが、大阪府庁だ。新型コロナ対策で職員は軒並み出勤。リモート取材どころか、「深夜に会見が開かれることも多く、日々の動きに対応するので精いっぱいだった」と府庁キャップは話す。積極的な発信で目立った吉村洋文知事。キャップは「前例のない感染症に対する府の取り組みを検証することが必要だ」と考えている。
直接会って相手の声、表情、空気を感じ取る。その大切さを記者が再認識した面もあるようだ。「関係を築いて情報を引き出すという仕事の性質上、オンラインや電話取材では代替できないものがある」とキャップの一人は話す。
一方でオンライン通話が、取材の可能性を広げたのは間違いない。直接会えなくても、顔を見て話せる。遠くにいても資料を共有しながら取材できる。「取材もリモートの流れが加速する」が記者たちの実感だ。「オンラインで顔が見えるやり取りを重ねたり、LINEで雑談したりするなど、取材先との新たな交流が求められる」と考える記者もいる。
新型コロナとの闘いは続く。「伝統的メディア」と言われる私たちの取材現場はどう変化するだろう。大切なものを守りつつ、進化する機会としていきたい。

羽根 和人(はね・かずと)氏
1969年9月生まれ、93年京都大文学部卒、朝日新聞社入社。前橋支局、鳥取支局、大阪本社社会部、東京本社社会部、広島総局次長、大阪本社社会部次長兼地域報道部次長、東京本社社会部次長兼地域報道部次長などを経て2019年5月から現職。