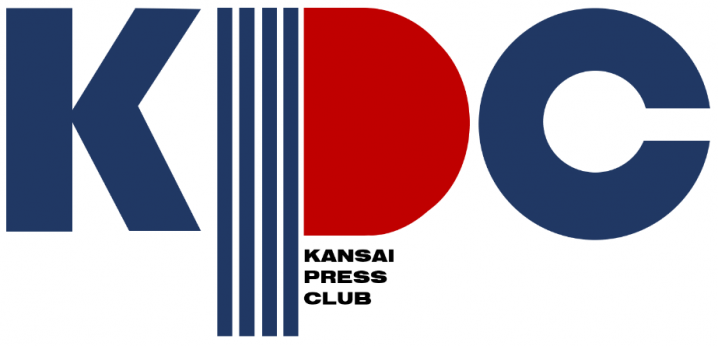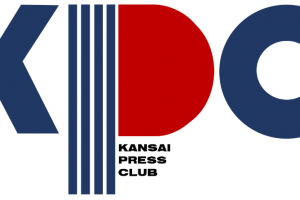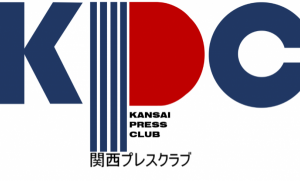3年目に入った新型コロナ禍、いつになっても世の中はすっきり明るくならないが、関西に住む者として「大大阪」復活への夢を、しばし語りたい。
「大大阪」をおさらいすると、大正後半から昭和初期にかけて大阪市が人口、面積、工業出荷額とも当時の東京市をしのぎ日本一の都市だった時代だ。大正14(1925)年の人口は211万人と世界で6番目。経済の繁栄とともに文化・芸術は盛んとなり、映画、音楽、ファッションなど大衆文化も花開く。阪急電鉄の創業者・小林一三氏が世界初のターミナルデパートを完成させた昭和4(1929)年もこのころだ。
大阪はパリ、ロンドン、ニューヨークと並ぶメトロポリスとなった。
約1世紀を経た今年、大阪中之島美術館が2月に開館、4月には大阪公立大学(Osaka Metropolitan University)が開学する。これを「大大阪」復活の狼煙(のろし)とみたくはないか。
大阪ガス会長で大阪商工会議所会頭を務めた大西正文氏(2014年死去)は1990年代半ば、「都市格」という言葉で「大大阪」の復活を志した。
人には人格があるように会社には社格、都市には都市格がある。その向上は再び大阪が世界のメトロポリスと伍するのに欠かせない。大西氏がとくに重視したのは、たとえば美術館、図書館、深夜も集えるレストランなど、経済効率一辺倒ではなく人々に潤いをもたらす空間だ。6000点に上る美の資産を収蔵した新美術館、知が集積する新大学が、望み通り今年、実現する。
大西氏が生真面目に「都市格」の言葉を繰り返した背景には、バブル後の社会・経済情勢があった。
自らの主張をまとめた著書「都市格について」を刊行した95年は、阪神大震災が発生し甚大な犠牲と被害をもたらし、地下鉄サリン事件が社会を震撼させた。木津信用組合、兵庫銀行が経営破綻、関西財界の一翼を担っていた大和銀行(現りそな銀行)のニューヨーク支店で巨額損失事件が発覚、これをきっかけに同行は再編の途をたどるのだが、営々と構築してきた日本の社会・経済システムが、壊滅的打撃を受けたその年だった。
大西氏の「都市格」は社会・経済全体の新たなあり方をも提言するものだった。
そして現在、新型コロナウイルスという全く異なる脅威によって、世界の社会・経済が激しく動揺している。だが、ワクチン、経口薬などにより、ようやく出口が見えなくもない。コロナ後の新たな社会・経済を進める時でもある。
「市格(都市格)」との言葉を最初に使ったのは、大大阪時代の中川望(のぞむ)・大阪府知事や関一(せき・はじめ)・大阪市長だったという。彼らが目指したのも効率主義ではなかった。美術館、大学、動物園や公共の託児所まで整備、文化や生活に配慮したまちづくりを進めた。
2024年のパリ五輪はセーヌ川で開会式を行うそうだ。翌年の大阪・関西万博も中之島を挟んだ土佐堀川、堂島川を、会場の夢洲(ゆめしま)までパレードする幕開けはどうだろう。
対岸に新美術館はじめとしたミュージアム群、上流には新大学のキャンパスが控える。狼煙が確実な前進につながることを夢見る。(田中 伸明)
事務局発55号