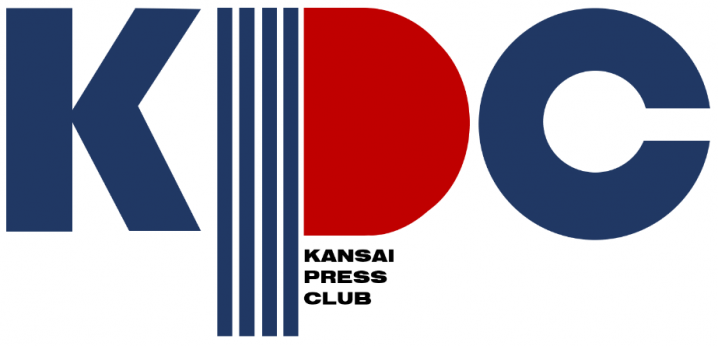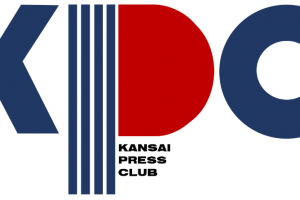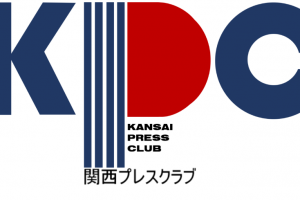令和元(2019)年も押し詰まった12月17日夕、大阪市内のホテルで「関西飛翔会」の解散総会が開かれた。同会は関西国際空港の計画・建設にかかわってきた産官学の約600人の有志によって、1988年に設立された。
前年に泉州沖で着工した関空は、大きなハンディを負ってスタートした。国際空港でありながら、事業主体は関西の自治体、民間企業も出資する株式会社方式。財政悪化のため国は建設費のすべてを持たなかった。しかも、高金利時代に1兆円の借入金を抱えた。さらに、海上での難工事やターミナルビルに国際コンペを採用したことなどで、建設費は当初見込みの1・5倍に膨れ、地元負担の重さなどから、必要性を疑問視する声がなおあった。
逆風下で関西飛翔会は開港に向けて応援団の役割をつとめた。
94年秋に開港にこぎつけた後も関空は批判にさらされる。黒字化の遅れから絶えず破綻会社と指摘され、与党幹部から、本四架橋、東京湾アクアラインと並ぶ「3大バカ事業」と称されたこともあった。非難が集中したのは、2本目の滑走路をつくる二期工事だった。
大手新聞などが二期反対の論陣を張った2000年代初め、飛翔会は代表幹事の吉川和広・京都大名誉教授らが中心となって「検証 関西国際空港の真実」(2001年2月)、「同Ⅱ」(02年3月)との冊子を発行した。
「二期工事はただちに休止すべきだ」「経営が行き詰まった会社が巨額の投資をすることは、民間の常識では考えられない」などの厳しい批判に対し、冊子は「利益を圧迫する最大の要因の支払い利息は低金利で着実に減り、アジアを中心に便数も伸びている」と、二期供用の目標年の2007年を待たず黒字化が可能であることを、具体的な数字を挙げて説明。
また、IATA(国際航空運送協会)の市場予測などを示して、「一本の滑走路の処理能力では2007年度までに限界に達する」と論理的に反駁し、二期推進を援護する手強いメディアとなった。
ただ、同時に大きな問題となっていた空港島の地盤沈下については、「情報開示しなかったことがマスコミの不信をまねき、世間に不安をあたえた」と関空側の対応の拙さを冊子は指摘した。甘やかすのではなく、関空を叱咤もしてきたのが関西飛翔会だった。
その後関空は、05年3月期決算で黒字を達成、二期のB滑走路は07年8月に2か月前倒しで供用を開始した。事業主体は変遷し、16年からは民間に運営権を売却するコンセッション方式となり、運営会社の関西エアポートの決算は最高益の更新を続けている。
解散総会は二十数人の小さな宴だったが、挨拶に立った旧運輸省出身の安田善守さんは「はなはだ寂しいが、関空は十分な機能を発揮し、なくてはならないインフラとなっている」と、満足感をもって会が役割を終える日を迎えた心境を語った。カルロス・ゴーン被告が関空から逃亡した理由は、米紙によると「動線の良さ」にあるという。不謹慎だが、関空の機能性が図らずも世界に実証された事件ともとれる。
元関空担当記者という資格で関西飛翔会の„最若手〝の会員だった当方は、さらに高度を上げ巡航速度を速めるだろう関空の行方を、今しばらくは見守っていきたい。(田中 伸明)
KPC事務局発51号