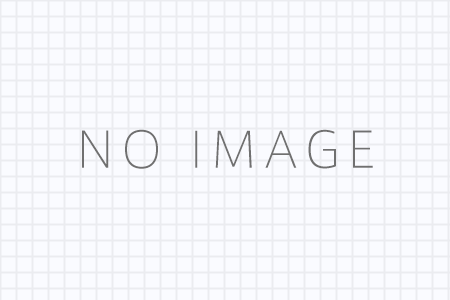2024年2月21日(水)
関西プレスクラブ30周年記念講演会「伝説の記者④」亀岡 典子氏
※公演の模様をYouTubeにUpいたしました※

「上方伝統芸能を〝翻訳〟する 悪戦苦闘の40年」
「古典芸能担当」と命じられたのは突然だった。私のような昭和30年代生まれは洋楽を聴き、ピアノを習うなど西洋文化の嵐の中で育った。和のモノはダサい、古くさいという感覚だったのでがく然とした。
楽屋へ取材に行ったとき、大幹部の楽屋は十何畳もあり次の間もある。どこまで近づいていいか分からず、座布団も出してもらえなかった。文楽の人間国宝だった初代吉田玉男の楽屋へ初めて行ったとき、「お茶出して」との声に「私は結構です」と遠慮したら「僕が飲むんや」と言われカルチャーショックを受けた。
取材中、俳優を名前ではなく、屋号で呼ぶこともある。「中村屋のおじさん」「成駒屋のお兄さん」と言われ、最初は頭の中が「?」でいっぱい。屋号を頭にたたき込んだら、次は「紀尾井町のおじさん」というように住んでいる町名で呼ぶ。さらに「◯代目」と代の数で呼ばれる人もいる。例えば六代目と言うと六代目尾上菊五郎のことだ。
脇の役名を覚えることも必要。「〇〇を演じたい」と言われても、「誰?」となると取材が深まらない。毎日本を読んで作品を覚え、家系図も頭にたたき込んだ。受験勉強をしている感じだった。
人間国宝の竹本源太夫が、長く上演されていない作品を復曲するというので取材した。最初は機嫌良く応じてくれていたが、知らない曲名が出たので「どういう作品か」と聞くと、「君は専門記者だろ」といきなり雷が落ちた。
ただ、これらは「この記者を育ててあげよう」との気持ちがあったのだと思う。
講演会の聞き手に私を指名してくれたことがある。30歳を過ぎた頃だった。私は「上手に話を聞き出すことができず、失敗した」と落ち込むばかりだったが、何回目かに「君、ちょっと上手くなったな」と言われた。竹本住太夫は何十年も芸歴があり、何でも話すことができるのに、私の知識が少ないと話の幅が狭くなる。最初はそれを我慢して「勉強しなさい」と言ってくれたのだと思う。本当に感謝している。
上方の芸能が低迷していた時期、上方歌舞伎の片岡秀太郎から30代の私と同世代の女性記者計4人に、「養子の片岡愛之助を中心に若者が見に来てくれる歌舞伎を作りたい」と声がかかった。秀太郎、愛之助、女性記者4人で何度も協議し実を結んだのが「平成若衆歌舞伎」。主役を勤めたのが当時は役名すらもらえなかったことのあった愛之助で、松竹がつくった上方歌舞伎塾を卒塾した若手が共演した。秀太郎の熱い思いに乗っからせてもらったのが正直な話だが、愛之助と一緒に関西の歌舞伎が盛り上がっていくのを応援できたと思う。
歌舞伎は隈取をして、見得を切ってと派手で華やかなイメージがある。だが上方歌舞伎は近松門左衛門の「曽根崎心中」「心中天網島」など町人の世界が舞台。見得もほとんどないし、隈取もなく、言葉も分かりやすい。市井の人たちの喜怒哀楽を描いている。東洋のシェークスピアと言われる通りの普遍性があり、現代でも起こり得る物語ということを読者に知ってもらいたい。
2012年に大阪市の橋下市長による文楽補助金削減問題が起こった。公演の動員ができていないことが問題視された。芸人は「必死に修業すればいい」という一面があり、次第に文楽側と市長の感情的なこじれに発展し、技芸員から不安の声が寄せられた。芸能は衰退すると復活は難しい。文楽は大阪で生まれ育ち、都市の格を上げる力がある。補助金問題がきっかけで衰退してはならないし、双方に誤解があるとも感じた。文化と行政の適切な関わり方を私たち文化部の記者が提示しなくてはいけないと感じた。
補助金問題のまっただ中、アルジェリア公演が企画された。民族も宗教も違うアフリカで文楽はどう捉えられるのか。取材で同行すると、若者が大勢観劇に来ていて驚いた。演目は 「曽根崎心中」で、公演後は涙を流す人もいた。日本の漫画がブームになっていて「本当の日本を知りたい」ということが理由。感想を聞くと「ドラマチックだ」「音楽がすごい」など。外国では高評価の文楽だが、日本では古典芸能は新聞以外の媒体で取り上げられることは少ない。私たちが工夫して書くことで日本人にも魅力を知ってもらいたい、との思いを強くした。
古典芸能の担当記者としての醍醐味は、何代にもわたって俳優を取材すること。人間国宝の片岡仁左衛門は父親の十三代目、長男の孝太郎、その息子の千之助と四代にわたって取材した。坂田藤十郎もそうで、息子の中村鴈治郎と中村扇雀、その息子の中村壱太郎、中村虎之介の三代だ。壱太郎の初お目見えは1歳ちょっとで「かわいいな」という印象だったが、大人になり遊女とか人妻とかを演じている。歌舞伎は役者の成長を見守る芸能。担当記者として大きな喜びを感じる。俳優側も同じで「記者を育てる」という視点があり、こうして互いの信頼関係ができる。
もう一つの醍醐味は悲しいことだが訃報だ。何十年も取材してきた俳優が亡くなったとき、どういう原稿を書くかが重要。限られた文字数で、素晴らしかった点、どんな芸能だったかを人柄とともに原稿にする。毎回、愛と感謝の気持ちを持ち、時には涙しながら書いている。きちんと紙面でお見送りをしたいと思っている。
古典芸能は奥が深く、何年やっても全てが分かるわけではない。だからこそ面白いし、驚きや感動がある。亡くなった坂東三津五郎は「インタビューは一期一会だ」と言った。記者は作品について勉強したか、インタビュー内容を把握し、ちゃんと記事にできたかを役者から見られる。逆に役者は役の解釈や舞台での演技を記者に判断される。互いに真剣勝負をしている。
私はいつも反省や自戒を繰り返しながら、深い感謝の気持ちをもって取材に向かっている。
【質疑応答】
―大学で講義をされているが、学生の反応は。
亀岡 一般に「古くさい」と思われている伝統芸能でも、今の学生には先入観がないため目新しく映っている。「なぜ伝統芸能は現代に必要なのか」と課題を出すと、「日本のいろんなモノが詰まっている」とのリポートが出るなど、意識の高さを感じる。
―補助金削減問題のような政策に対し、メディアの力は「意外に弱い」と感じた。文化と行政に関し、メディアの力をどう考えるか。
亀岡 補助金削減問題を機に第三者機関の大阪アーツカウンシルが設立され、行政と文化が適度な距離を持つことができるようになった。メディアは両方を客観的に見ることができ、橋下市長が主張した「動員努力」にも一理あると思った。ただ芸の中身に対して口を出したことは疑問だった。メディアは信念に従い書き続けるしかない。(文中敬称略)

人間国宝のみなさんに専門記者として育てられたと語る亀岡典子さん(関西大学梅田キャンパス・大ホール)
文楽補助金削減問題などに自身の見解を示す亀岡典子さんの話に参加者らは耳を傾けた。
(中田 信治)
亀岡 典子(かめおか のりこ)氏
略歴(講演時)=1990年、産経新聞社に入社。文化部で30年以上にわたって、歌舞伎、文楽、能など古典芸能を中心に演劇を担当。おもに上方の芸能について取材、執筆活動を続けている。パリ・オペラ座で史上初めて行われた歌舞伎公演やアルジェリアの文楽公演などに同行取材。紙面で劇評、インタビュー記事などのほか、コラム「離見の見」「古典の夢をみる」「芸魂」を連載。
大阪市による文楽協会への補助金削減問題では、文化と行政の関係を掘り起こす連載を共同執筆した。2020度から神戸学院大学人文学部の非常勤講師を務めている。著書に『文楽ざんまい』(淡交社)、『夢―平成の藤十郎誕生―』(同)など。